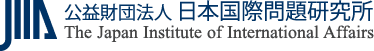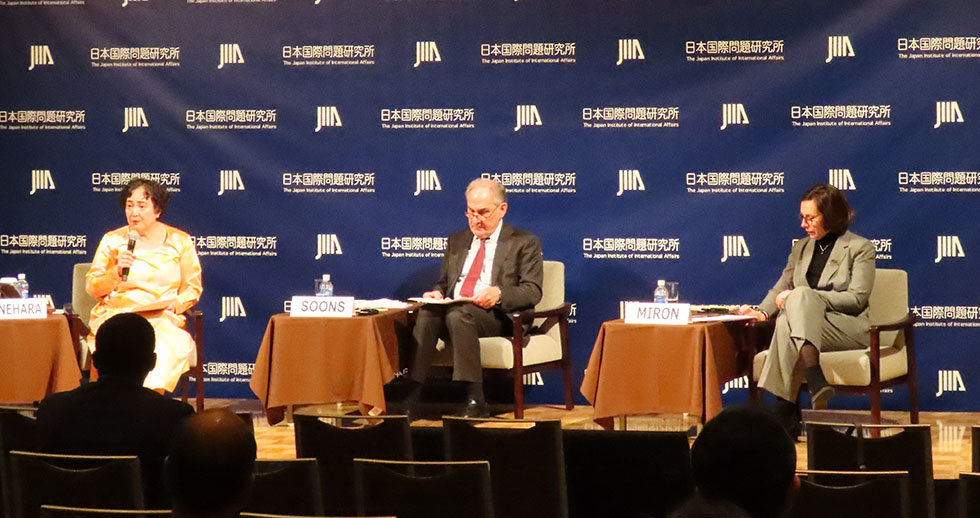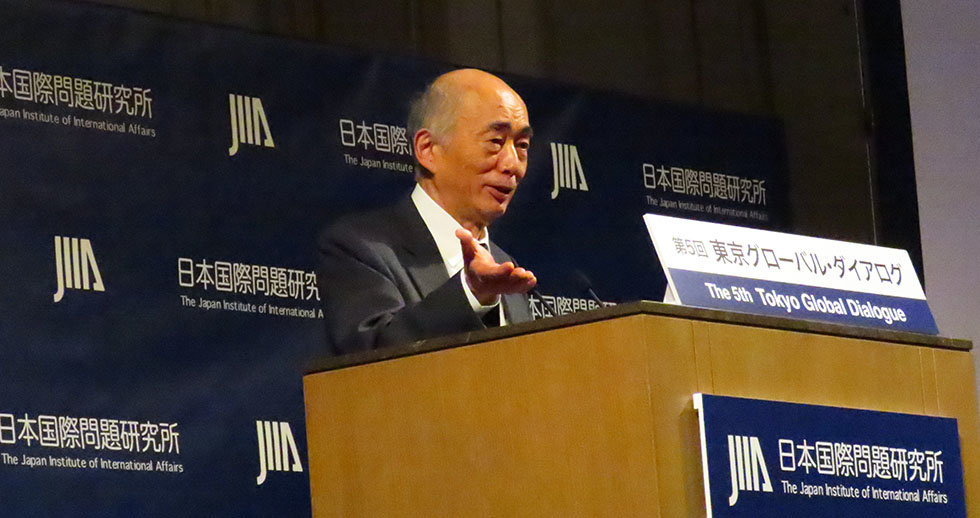公益財団法人日本国際問題研究所は、1月29日(水)及び同月30日(木)、第6回東京グローバル・ダイアログ(TGD6)をThe Okura Tokyoにおいて開催しました。本年のテーマは「グローバル・レジリエンスへの挑戦 (A Quest for Global Resilience)」で、会議の冒頭、挨拶に立った佐々江理事長は、「このテーマには、ポスト冷戦期の世界が育んできたガバナンスの力が国際社会から失われつつあるとの危機感とともに、自由主義陣営の一員である日本が、その復活・再生に努めなければならないという強いメッセージが込められています」と述べました。
初日となる1月29日は、「米新政権と国際秩序」、「20世紀史からの教訓」、そして「欧州の安全保障情勢」をテーマとするセッションで議論を行いました。初日の最後には、石破茂内閣総理大臣にご挨拶いただきました。続く2日目(30日)は、「国際の平和と安全におけるAI」、「インド太平洋のチョークポイント」、「グローバル・アーキテクチャーの再構築」をテーマとするセッションで議論を行い、締めくくりに佐々江理事長が閉会の辞を述べ、2日間の日程を終えました。
1.概要
(1)日時
2025年1月29日(水) 13時から19時20分
2025年1月30日(木) 9時30分から15時30分
【プログラム】 https://www.jiia.or.jp/TGD/tgd6/
(2)場所
The Okura Tokyo(東京都港区)及びオンライン
(3)参加人数(会場参加はご招待のみ、会場参加・オンライン参加ともに事前登録者概数)
会場参加:約400名
オンライン参加:約800名
2.主な登壇者:約10の国・地域から計約40名が登壇
【ご挨拶】
石破茂内閣総理大臣
【登壇者】 ※姓によるアルファベット順
秋山信将 日本国際問題研究所軍縮・科学技術センター所長
マリ=ドア・ブザンスノ NATO広報担当事務総長補
ジャン=クリストフ・ブーシェ カルガリー大学准教授
ヴィクター・チャ 米戦略国際問題研究所(CSIS)地政学・外交政策部長兼韓国チェア、ジョージタウン大学特別名誉教授
パトリック・M・クローニン ハドソン研究所アジア太平洋安全保障部長、カーネギーメロン大学客員研究員
ビル・エモット 国際問題戦略研究所(IISS)理事長
オーファー・フリッドマン キングス・カレッジ・ロンドン上級講師
ナヴィン・ギリシャンカー 米戦略国際問題研究所(CSIS)経済安全保障技術部長
ブレンダン・グローヴズ Skydio(スカイディオ)社最高法務・渉外責任者、元米司法省次官補
ジャスティン・ヘイハースト 駐日オーストラリア大使
彦谷貴子 学習院大学国際センター教授
堀江和宏 防衛装備庁防衛技監
細谷雄一 慶應義塾大学教授
市川恵一 内閣官房副長官補兼国家安全保障局次長
伊藤錬 株式会社サカナAI共同創業者兼COO
ヤクブ・ヤコーブスキー ポーランド東方研究所(OSW)副所長
神保謙 慶應義塾大学教授
ビラハリ・コーシカン シンガポール国立大学中東研究所会長
鹿山真吾 デロイトトーマツ合同会社ストラテジー・リスク・トランザクションリーダー、デロイトアジアパシフィックテクノロジーセクターリーダー
柯隆 東京財団政策研究所主席研究員
北村滋 元国家安全保障局長
城内実 経済安全保障担当大臣
倉田秀也 防衛大学校教授、日本国際問題研究所客員研究員
バラク・クシュナー ケンブリッジ大学教授
桒原響子 日本国際問題研究所研究員
トーマス・ルカシェク 元大使、ワルシャワ大学講師(同大学で博士号取得)
フェデリカ・モゲリーニ 欧州大学学長、前EU外務・安全保障政策上級代表
中西寛 京都大学教授
中満泉 国連事務次長兼軍縮担当上級代表
ヴィピン・ナラン マサチューセッツ工科大学核安全保障フランク・スタントン教授
大矢伸 双日総合研究所チーフアナリスト
朴喆煕 駐日大韓民国大使
ハンノ・ペヴクール エストニア共和国防衛大臣
H. K. シン デリー政策グループ(DPG)所長、元駐日インド大使
ランドール・シュライバー プロジェクト2049研究所理事長、パシフィックソリューション・パートナー
ノア・スナイダー エコノミスト誌東アジア支局長
ジョシュア・W・ウォーカー ジャパン・ソサエティー理事長
呉軍華 日本総合研究所上席理事
3.議論の概要
(1)1月29日(水)
①米新政権と国際秩序:日本の立ち位置
- トランプ第二期政権が発足したが、ワシントンの政策コミュニティ―は同政権の方向性を把握しきれてはいないという指摘が挙がった一方、トランプ大統領は各イニシアティブの相互連関に関心を払っておらず、結局のところトランプ大統領のもとに様々な政策グループが統一されていくだろうとの指摘がありました。
- しかし、米国のインド太平洋政策には、米中間の戦略的競争関係を背景に、オバマ政権、トランプ第一期政権、バイデン政権、トランプ第二期政権へと続く連続性があるとの指摘がありました。そして、トランプ政権発足後の初動としては、日米間の対話のチャネルを確保し、信頼関係を強化することの重要性が強調されました。さらに、日本を含む各国は自国のために何をしようとしていて、米国のために何ができるのかを首脳会談でトランプ大統領に率直に説明することで関係を強化することは十分可能であるとの指摘もありました。
- インド太平洋地域の安全保障環境は厳しさを増しており、「力による平和」を標榜し同盟国に防衛負担増を求めるトランプ大統領の登場にかかわらず、日本は現実の危機に見合う防衛力の強化を自主的に行うべきであると指摘されました。
- さらに、サイバー、人工知能(AI)、ドローン等の新興技術の重要性が強調され、これらの分野における日米の産業協力の重要性も強調されました。USスチールの買収問題も同様に、日米間の産業界の信頼関係の構築が今後より一層重要になろうという見解の一致が見られました。
- また、「タリフ・マン」を自称するトランプ大統領にとって関税はあくまでも交渉材料であることを理解し、必要以上に恐れず胸襟を開いて交渉する必要性が指摘され、過度な高関税がインフレを始めとする米国経済に及ぼす影響についても注視し、交渉にあたるべきと議論されました。
- トランプ大統領の国際秩序に対する関心の低さ、同盟国を蚊帳の外に置いたディールを行う危険性、意に添わない国に懲罰的な関税をかける構えを崩さないといった点を懸念する声が複数挙がりました。また、トランプ大統領は交渉の際に西側のリーダーにはバッド・コップを演じ、プーチン大統領や金正恩主席にはグッド・コップを演じるとの指摘もありました。
②20世紀史からの教訓:世界戦争と冷戦の時代
- 本セッションでは、二度の世界大戦と冷戦を経験した20世紀の歴史をたどり、現在の日本と国際社会が直面する課題について検討されました。
- 東アジアでは歴史が政治的に利用されることがあり、歴史をめぐる問題に決着をつけることは難しいものの、現在と将来の努力を積み重ねることで、和解につながる可能性が提示されました。現在の我々は「20世紀の終焉の終焉」を目撃しており、日本はあらためて国家戦略を考える必要があるという指摘もありました。
- グローバル・ヒストリーの視座から、現在の日本が直面する課題をどのように理解することができるかについても議論されました。1919年のパリ講和会議において日本が提示した「人種差別撤廃案」を事例として、日本の行動が及ぼし得るインパクトはグローバルなものであり、それに自覚的である必要性が指摘されました。
- フロアからも、安定した国際秩序の再構築には発展途上国を包摂する必要があり、その点にこそ日本が果たし得る役割があるのではないかという議論が提示されました。また、近代以降の歴史を長期的に俯瞰すると、過去の大戦に匹敵するような紛争が近い将来起こる兆しがあるのか等、歴史のアナロジーで考える論点が出されました。
③欧州の安全保障情勢がインド太平洋に与える影響
- 「欧州の安全保障情勢がインド太平洋に与える影響」セッションでは、ウクライナ紛争の地政学的な影響に焦点が当てられました。
- 基調講演を行ったぺヴクール・エストニア防衛大臣は、北朝鮮・中国・イランの支援など新たな枢軸の協力を得たロシアをウクライナ戦争で勝利させてはならず、その戦争の負担をウクライナに押し付けることは認められない旨を強調し、民主主義諸国はウクライナを支援することで、ロシアにとっての戦争のコストを上げることが必要だと述べました。バルト諸国の国防費は既にGDP5%以上に達しており、その中でもエストニアは最も高いことを明らかにし、他の全てのNATO諸国に一層の努力を求めました。その上で、戦争終結には、ロシアがウクライナに与えた損害を賠償するといった公正な平和(just peace)、そして持続的な平和(lasting peace)の保証、更にこれらを実現するための強制力、すなわち軍事力が必要であると主張しました。
- パネリストたちは、ウクライナ戦争が世界の抑止力、特にインド太平洋地域に与える影響や、ロシアによるウクライナへの影響工作の実相について議論を交わすとともに、アジアにおける現状変更の試みを抑止するためにも、ウクライナ戦争をどう終わらせるかは決定的に重要であるとの点で意見の一致が見られました。
- 極右政党の台頭を始めとする欧州や米国での内政の混乱が対外政策や民主主義秩序を揺るがしていることにも議論が及びました。偽情報に対抗し、民主主義の回復力を確保するための戦略的コミュニケーション、教育、国際協力の重要性が強調されました。
④【ご挨拶】石破茂 内閣総理大臣
(首相官邸HP)
令和7年1月29日 第6回東京グローバル・ダイアログ | 総理の一日 | 首相官邸ホームページ
(外務省HP)
石破総理大臣の第6回東京グローバル・ダイアログへの参加|外務省
(2)1月30日(木)
①国際の平和と安全におけるAI(人工知能)
- AIの急速な進展に伴う安全保障上の課題について議論された。米ソ(露)間では、新興技術の急速な発展により非対称性が生じても、それが単独で戦略的均衡を崩したことは少なく、AIの普及が非対称的優位性(enduring asymmetrical dominance)を長期的にもたらすことはないと分析しました。しかし、目標(targeting)やISRで大きな効果をもたらすことで「持てる者」と「持たざる者」の格差を拡大させるリスクがあり、国際的な安全保障環境が悪化する可能性が憂慮されると述べました。
- また、AIの軍事利用、とりわけ核兵器の運用に関しては、人間の関与(human in the loopまたはhuman control)を維持することが不可欠であり、AIの可能性を最大限に活かしつつも、人類の安全を確保するための監視と制御が優先事項であるとの認識が共有された。
- 大国以外の国連加盟国は、AIを始めとする新興技術を使いこなすことができず、その発展において機会よりもリスクを感じており、AIに関する異なる視点を共有するために、多国間の包摂的なフォーラムが不可欠であるとの認識が示されました。
②インド太平洋のチョークポイントを語る:台湾海峡・南シナ海・東シナ海・朝鮮半島
- インド太平洋における地政学上の重要な要衝であり、それぞれが将来的に紛争のホットスポットになる可能性を秘めている台湾海峡、南シナ海、東シナ海、朝鮮半島は、第2期トランプ政権発足後にどのように変化し、国際社会はどのように対応すべきかについて議論が交わされました。
- 複数のパネリストから、インド太平洋にはチョークポイントというより「断絶(fault lines)」が広がっているという見方が示されました。トランプ政権は中国にとって牽制となっており、短期的には米中間の衝突はなく安定的な状況が継続するとの指摘がありました。ロシアとの関係を深める北朝鮮の対米関係の行方や、北朝鮮の核戦力の増強及び抑止から戦術核の先制使用へと変化した核ドクトリンの危険性といった問題も議論されましたが、トランプ大統領は当面、ウクライナ戦争の終結が優先事項であり、非核化よりも北朝鮮の対ロ支援を止めることに関心があるという指摘もありました。韓国の政局に関わらず、日韓や日米韓の協力、自由で開かれたインド太平洋は韓国の国益であるとの指摘もありました。
③グローバル・アーキテクチャーの再構築は可能か
- 本ダイアログのテーマである「グローバル・レジリエンスへの挑戦」に沿って、これまでに行われた議論を振り返り、国際社会がグローバル・アーキテクチャーにレジリエンスを取り戻せるかについて議論されました。トランプ政権登場のポジティブな側面と、ネガティブな側面、グローバルサウスから見た国際秩序やガバナンスの評価、ルールに基づく国際秩序やグローバル・アーキテクチャーが機能する条件、ミニラテラルやパートナー国の連携の有用性などについても議論が及びました。
④ クロージング
- 佐々江理事長が2日間の議論を総括し、今回のTGDではトランプ政権について議論が集中したとしつつ、以下を述べました。「昨年の東京グローバル・ダイアログのクロージングで私は、『仮にトランプ政権が誕生しても、大統領の発言は重いがその言動に過剰反応するのではなく、行動をよく見て、慎重に政策を進めていくことが重要であると思う』と述べました。二期目のトランプ政権が発足した今、この視点は重要性を増していると感じます。各国が自ら必要と考える政策を強い覚悟で進める必要があります。」一方で、トランプ政権は予測不可能性が高いことは事実であり、自由主義陣営の各国が政策協調と相互理解を進めていくことが重要であって、「月並みな結論だが「対話」こそが、自由主義陣営の各国を疑心暗鬼に陥らせない唯一の道である」と述べ、会議を締めくくりました。
以上