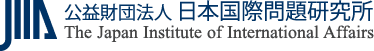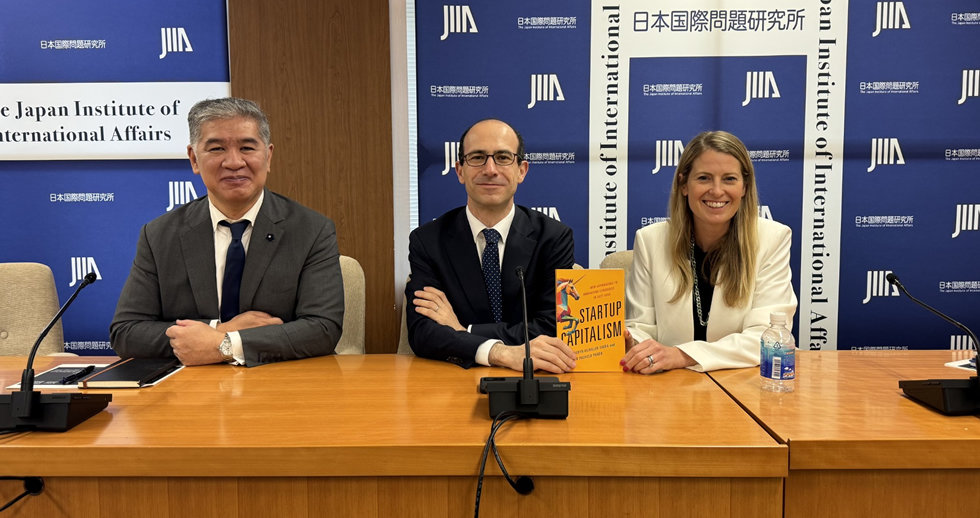登壇者:
-
ロビン・クリングラー・ヴィドラ博士
グローバル・エンゲージメント担当副学部長、キングス・カレッジ・ロンドン、キングス・ビジネス・スクール政治経済学・起業家論リーダー -
ラモン・パチェコ・パルド教授
キングス・カレッジ・ロンドン欧州・国際関係学科学科長・国際関係学教授
登壇者はまず、政府が新興企業支援に力を入れるようになったことを指摘し、この関与を国の競争力を高めるための広範な戦略の一環と位置づけた。これは経済政策の真の転換なのか、それとも既存のモデルの適応なのか対談では、今日の新興企業支援の目的が、シュンペーター的な「創造的破壊」パターンで既存の経済構造を変革することにあるのか、それとも国の強みを強化することにあるのかを探った。
新興企業支援をめぐる政府のレトリックは、既存の経済や競争力の枠組みにおける革新や破壊を示唆することが多いが、追求されていることの多くは、特に北東アジアにおいて、確立された経済モデルとの高度な継続性を反映している。
登壇者は、「スタートアップ資本主義」と呼ばれる概念的枠組みを紹介した。そこでは、スタートアップ企業は単にイノベーションの担い手としてだけでなく、技術的競争力と経済的安全保障を強化するための重要な資源として扱われ、自国がグローバル経済において優位性を維持できるようにしている。東アジア諸国(中国、日本、韓国、台湾)の新興企業は、既存企業に挑戦するのではなく、国家主導の経済戦略の中に、程度の差こそあれ、ますます組み込まれている。
日本の場合、スタートアップは必ずしも系列に挑戦するのではなく、日本経済全体を強化するために系列と協力することが増えている。この連携は、2023年までに20のユニコーンを育成することを目標とした、経済産業省とジェトロ(日本貿易振興機構)が2018年に立ち上げたJ-Startupイニシアチブが証明しているように、政府によって奨励されている。しかし、この目標は達成されず、 、新たに誕生したユニコーンはわずか4社にとどまった。それなのに、このプログラムは100のユニコーンを生み出すという新たな野望を掲げて継続されている。
長年にわたり、日本政府は、より柔軟な労働環境へと徐々に移行し、例えば、常用雇用に関する規範を緩和することで、より多くの起業活動を可能にしてきた。日本はまた、イノベーター・ビザなどの政策手段を導入し、外国人人材を誘致してきた。また、日本ではベンチャー・キャピタルに利用できる資金が大幅に増加しており、現在では世界で最も活発なコーポレート・ベンチャー・キャピタル企業の半分を誇っている。特筆すべき例として、三井住友銀行が支援する神戸市と米国を拠点とするファンド500 Startupsとの提携がある。
ディスカッションでは、日本のモデルはおそらく他の3カ国よりも安定的で保守的である一方、2度目の起業を奨励し、失敗のスティグマを下げるための規制変更などの政策を通じて進化していることが浮き彫りになった。「スタートアップ資本主義」における様々なアプローチを理解するためには、リスク許容度における文化の違いが不可欠である。
韓国は、国家主導の協調的アプローチのもう一つの例を示している。2014年、政府は18の創造経済革新センター(CCEI)を設立し、各センターはチェボル(韓国財閥)と連携し、特定の産業における新興企業の育成に注力している。このモデルは、既存財閥と新興企業との緊密な連携を促進する。
さらに最近では、韓国政府は2023年にK-Startup Grand Challengeを立ち上げ、国内外の起業家に地元のスタートアップ・エコシステムへの貢献を呼びかけている。これを促進するために、新しい起業家ビザが導入された。これは、外国人投資家や起業家が国のイノベーション能力を維持するために不可欠であるという信念を反映したものである。このビザは、外国人起業家が財閥にアクセスすることも可能にする。
台湾は、このような地域情勢の中では異端児のような存在である。早くから、中小企業はサプライヤーであると同時にイノベーターでもあり、中国を前にした国家安全保障の観点からの存立の必要性に応えるものであった。台湾政府は新興企業への株式投資を徐々に拡大し、日本や韓国とは異なり、台湾の新興企業政策は既存の企業や能力を強化することに重点を置いておらず、新しい能力を育成することに重点を置いている。
2017年、政府はグリーンエネルギー、モノのインターネット、新技術などの新興セクターへの株式投資を拡大した。このような方針は、TSMCの創業者であるモリス・チャン氏から批判を受けた。 政府が既存の企業だけでなく、主に新しい活動や能力においてイノベーションを育成する方向にシフトしていることを示す新たな証拠となった。
中国は、業界によってこれらすべてのモデルが混在している。電子商取引のような分野では、新興企業が既存企業と直接競争することが認められており、アリババのような巨大企業の台頭につながっている。対照的に、半導体やAIのような戦略的分野では、長期的な国家目標を達成するために政府が新興企業と既存企業との協業を促進するという、より協力的な枠組みが特徴となっている。
調査対象の4カ国の中では、中国モデルがおそらく最も効率的であろうが、中国と他の3カ国との間にかなりの規模と力の差があることを考えれば、このような比較をするのは不公平であろう。
対談は、こうした動きが理論的に持つ意味合いについて考察することで締めくくられた。伝統的に、新興企業はシュンペーターの創造的破壊理論に沿った破壊者として称賛されてきた。しかし、北東アジアの文脈では、新興企業は既存の経済構造の中に組み込まれることが多く、既存の経済構造を破壊するのではなく、むしろ強化する役割を果たしている。新興企業と既存企業とのコラボレーションと相互利益を重視するオープン・イノベーションのパラダイムが支持を集めている。政府は新興企業を、必ずしも支配的な秩序に挑戦することなく、競争上の優位性を高めることができる国家資源として位置づけるようになってきている。したがって、新興企業が技術、安全保障、経済成長における長期的な国家目標に貢献することで、破壊よりも統合が重視されるようになっている。