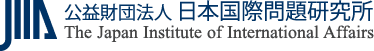下條正男・拓殖大学名誉教授より寄稿いただいた論考を掲載します。なお、論考は執筆者の見解を表明したものです。
韓国の「東北アジア歴史財団」は2023年12月27日、『韓日古地図の中の朝鮮半島、東海そして独島』を同財団のサイトに公開した。その中で著者の一人である金鍾根氏は、于山島を独島とする前提で『新増東国輿地勝覧』所収の「八道総図」と鄭尚驥の「東国大地図」を読図し、そこに描かれている于山島を独島と断じていた。
だがそれは誤りである。それは次の二点についての反証ができなければ、「八道総図」と「東国大地図」の中の于山島を独島とすることはできないからである。
その第一点、「八道総図」の于山島は確かに独島だったのかどうか、ということである。それは1996年、『現代コリア』5月号(第361号)所収の拙稿「竹島問題考」で、韓国側が于山島を独島とする唯一の文献である『東国文献備考』(1770年)の分註(注1)について論じ、その分註が編纂の過程で改竄されていた事実を明らかにしているからである。『輿地志』を引用し、「于山は倭の所謂松島(現在の竹島)なり」としている分註は、原典の『輿地志』では「一説、于山欝陵本一島」として、于山島と欝陵島を同島異名の島としていたからである。それを『東国文献備考』の分註では、「一説、于山欝陵本一島」としていた原典からの引用文を「于山は倭の所謂松島(現在の竹島)なり」と書き換え、欝陵島を松島としていたのである。
従って金鍾根氏は、「八道総図」と「東国大地図」の中の于山島を独島とする前に、于山島と欝陵島を同島異名としていた『輿地志』が、何故、『東国文献備考』の分註では独島とされていたのか、その論証を済ませておかねばならなかったのである。これが第二点である。
そこで本稿では、その二点についての文献批判を怠った金鍾根氏の文献解釈の誤りについて、その事実を明らかにしたのである。
1.『世宗録地理志』と于山島
金鍾根氏は、『新増東国輿地勝覧』所収の「八道総図」と鄭尚驥の「東国大地図」に描かれた于山島を独島と解釈した。だが前者と後者の于山島は全く異なる于山島で、いずれも独島(竹島)ではなかったのである。
それを金鍾根氏は、「独島関連の地図の中で、朝鮮前期を代表する地図は『新増東国輿地勝覧』に載せられている『八道総図』である」として、「八道総図」に描かれた于山島を独島としていたのである。
しかし『新増東国輿地勝覧』(「蔚珍縣条」)の分註では、「一説、于山欝陵本一島」として、于山島と欝陵島を同島異名の一島としていた。『新増東国輿地勝覧』(「蔚珍縣条」)所収の一説では、于山島は独島ではない、としているのである。それを金鍾根氏は、『新増東国輿地勝覧』所収の「八道総図」に言及しながら、『新増東国輿地勝覧』についての文献批判を怠っていたのである。
それにこの『新増東国輿地勝覧』(「蔚珍縣条」)に記された于山島は、『世宗実録地理志』(「蔚珍縣条」)の于山島に由来し、韓国側の竹島研究ではそれを根拠として、独島(竹島)を韓国領としてきたのである(注2)。『世宗実録地理志』(「蔚珍縣条」)には、于山島と欝陵島(武陵島)について次のように記されているからである。
于山、武陵の二島、縣の正東の海中に在り。〔分註〕二島、相去ること遠からず。風日清明なれば則ち望み見るべし。
韓国側の竹島研究では、分註にある「二島相去不遠。風日清明則可望見」(二島、相去ること遠からず。風日清明なれば則ち望み見るべし)を解釈して、その于山島と武陵島(欝陵島)の二島はそれほど離れておらず、晴れた日には欝陵島から独島が見えるので、その于山島は独島に違いないとしたのである。金鍾根氏もまた、その主張に従ったのであろう。
だが地理志及び地誌が編纂される際には、予め編集方針が定められていたのである(注3)。それは地理志及び地誌にはおのずから読み方があった、ということである。『世宗実録地理志』の場合、その編集方針は「規式」と呼ばれ、『東国輿地勝覧』の時も編集方針としての「地理誌続撰事目」が作られていた。そのいずれの場合も、島嶼は管轄する官庁から海島までの方位と距離を記すことになっていた。そのため『世宗実録地理志』では「在縣正東海中」として、欝陵島は、蔚珍縣からみて「正東」の海中に在り、欝陵島は蔚珍縣から「見える」距離にあると読まなければならなかったのである。
ところが戦後、1960年に申奭鎬氏が『思想界』で「独島の来歴」と題して論稿を発表して以来、『世宗実録地理志』(「蔚珍県条」)の「見える」を欝陵島から独島が「見える」と解釈し、地志が「規式」に従って編纂されていた朝鮮史研究の伝統を忘れ、今日に至ってそれが定説となっているのである(注4)。
しかしその「見える」は、『新増東国輿地勝覧』(「蔚珍縣条」)では若干修正がなされ、次のように記されていたのである。
于山島 欝陵島〔分註〕 一に武陵といい、一に羽陵という。二島、縣の正東の海中にあり。三峰岌業として空を撑(支)え、南峯やや卑(低)し。風日清明なれば則ち峯頭の樹木及び山根の沙渚、歴歴見るべし。(中略)一説に于山欝陵本一島。
『新増東国輿地勝覧』(「蔚珍縣条」)では、「よく晴れた日には、島の上部には樹木が見え、島の根元には沙渚が歴歴と見える」(「風日清明則峯頭樹木及山根沙渚歴歴可見」)としたのである。この歴歴と「見える」島は欝陵島のことで、岩礁に過ぎない独島ではない。それに『新増東国輿地勝覧』(「蔚珍縣条」)の記述は「規式」に倣って欝陵島について記したもので、于山島に関しては何も記されていない。あっても「一説、于山欝陵本一島」としているだけで、それも于山島は欝陵島と同島異名とされている。
それが後代の『輿地図書』(1757~1765年)になると、『新増東国輿地勝覧』を踏襲しながら于山島はその姿を消している。それは17世紀から18世紀になると、韓百謙の『東国地理志』や李孟休の『春官志』等が編述され、そこでは于山島と欝陵島を同島異名の島としていたからである(注5)。
金鍾根氏は、『新増東国輿地勝覧』所収の「八道総図」の中の于山島を独島としていたが、その『新増東国輿地勝覧』では「一説、于山欝陵本一島」として、于山島を欝陵島とは同じ島としていた。これは『東国輿地勝覧』(後に『新増東国輿地勝覧』)に「八道総図」が載せられた当時、于山島に関しては、確かな地理的理解がなかったからである。事実、『東国輿地勝覧』の編纂に関わった梁誠之は、『高麗史』(「地理志」)の編纂にも従事していたが、『高麗史』(「地理志」)では「一云、于山武陵本二島」として、于山島と欝陵島を別々の二島としていたのである。梁誠之は、于山島の所在を明確にすることができなかったのである(注6)。
そのため『新増東国輿地勝覧』所収の「八道総図」と「江原道図」の于山島は、欝陵島の西側にその三分の二程の大きさに描かれ、分註では「一説、于山欝陵本一島」として、後世の研究を俟ったのである。
それを金鍾根氏は、文献批判を怠り、『新増東国輿地勝覧』所収の「八道総図」に描かれた于山島を独島と断じたが、その于山島は所在を明確にできなかったもう一つの欝陵島(注7)であった。金鍾根氏は次の「東国大地図」の解釈でも同じ過ちを犯していたのである。
2.鄭尚驥の「東国大地図」
金鍾根氏は、鄭尚驥の「東国大地図」に于山島が描かれていることに注目した。「八道総図」では于山島が欝陵島の西側に描かれていたが、鄭尚驥の「東国大地図」では欝陵島の東側に描かれていたからである。そこで金鍾根氏は、鄭尚驥の「東国大地図」を欝陵島と于山島の位置が正しく表現された最初の地図としたのである。
その理由について、金鍾根氏は、「この地図が作られて以後に製作された大部分の地図では、于山島が欝陵島の東側に描かれている。このような欝陵島と于山島の位置の変化は、安龍福事件を契機として起こった欝陵島争界を通じて、正された結果であった」と記したのである。
だが金鍾根氏は、鄭尚驥の「東国大地図」に何故、于山島が描かれていたのか。またその于山島が独島であったとする論証もできていない。金鍾根氏は、「于山は倭の所謂松島(現在の竹島)なり」とした前提で、「東国大地図」の于山島を独島と独断したのであろう。
論考の中で、金鍾根氏は「欝陵島と于山島の位置の変化は、安龍福事件を契機として起こった欝陵島争界を通じて、正された結果」としたが、実際の独島は欝陵島の東南に位置し、欝陵島からは90㌔近くも離れている。それに鄭尚驥の「東国大地図」に描かれている于山島は欝陵島の東北にある。その于山島を独島とするのは無理がある。
確かに金鍾根氏が主張するように、「欝陵島と于山島の位置の変化は、安龍福事件を契機として」起きていた。それも1696年、安龍福等が鳥取藩に密航し、江戸幕府の命を受けた鳥取藩によって追放された安龍福の密航事件が契機となって、朝鮮政府では欝陵島捜討使を欝陵島に派遣することになったからである。その際、欝陵島捜討使達は欝陵島を描いた『欝陵島地図』とともに欝陵島の状況を復命することになっていた。その欝陵島捜討使の中で、1711年に朴錫昌が描かせた『欝陵島図形』がその後の欝陵島地図に大きな影響を与えることになったのである。朴錫昌の『欝陵島図形』には、欝陵島の東側に「所謂于山島」とした小島が描かれているからである。
だが「所謂于山島」と注記された小島が独島でないことは、そこに「海長竹田」と記していることからもいえるのである。岩礁に過ぎない独島には、「海長竹」は叢生していないからである。
それに1694年、欝陵島を捜討した張漢相も、『欝陵島事蹟』の中で欝陵島の東五里(約2㌔㍍)程に一小島があって、そこには海長竹が叢生している(「東方五里許有一小島。不甚高大而海長竹叢生」)としていたのである。それにこの小島が独島でないことは張漢相自身、「東の海中を望めば一島あり。杳(遥か)辰(東南東)の方に位置して、その大きさ欝陵島の三分の一に過ぎず、三百余里(「東望海中有一島杳在辰方而其大未満蔚島三分之一不過三百余里」)として、欝陵島の辰(東南東)の方位にある独島を目撃しているからである。
これは張漢相が復命した欝陵島の東五里程の小島と、朴錫昌が「所謂于山島」とした小島は同じ島だったということである。そこには「海長竹田」があり、「海長竹が叢生」していたからである。この「所謂于山島」は、現在の竹嶼(チクトウ)のことである。
さらに歴史的事実として、安龍福は、「于山島は欝陵島の東北」にあると供述していたからである(注8)。朴錫昌が「所謂于山島」と注記したのは、そこが所謂、于山島だったからである(注9)。
金鍾根氏は、鄭尚驥の「東国大地図」に于山島が描かれているとそれを独島とした。だがそれは張漢相が「東方五里」程にあるとした小島のことで、現在の竹嶼である。その竹嶼が、鄭尚驥の「東国大地図」で于山島と表記されたのは、朴錫昌の『欝陵島図形』を基にして作図されていたからである。
鄭尚驥は「東国大地図」を朝鮮の八道の「分図」として、地図帖に載せていた。その地図帖は、金鍾根氏が論考の中で列挙している『海東地図』、『輿地図』、『地乗』、『広輿図』、『八道輿地図』等のことで、その地図帖に収録されている「欝陵島図」はいずれも朴錫昌の『欝陵島図形』を底本としているからである。その証拠は、いずれの「欝陵島図」にも朴錫昌の『欝陵島図形』からはじまった「所謂于山島(または于山島)」、「刻石立標」(注10)、「刻板立標」と五つの小島が描かれているからである。
鄭尚驥の「東国大地図」に描かれている欝陵島は、朴錫昌の『欝陵島図形』に模して作図された「欝陵島図」を基にしていたのである。
この事実は、鄭尚驥の「東国大地図」に描かれている于山島は独島ではなく、朴錫昌の『欝陵島図形』に由来する竹嶼だったということなのである。
『八道総図』と鄭尚驥の「東国大地図」には、いずれも于山島が登場してくる。だがその于山島は、もう一つの欝陵島であり、竹嶼のことであった。「于山島は独島」と言った前提で文献や古地図を読図する限り、歴史の事実は見えてこないのである。
注1.1996年から1998年にかけ、韓国の月刊誌『韓国論壇』誌上で、韓国国防大学校教授の金柄烈氏と竹島問題に関する論争を行なった。その『韓国論壇』(1998年8月号)で「竹島問題の問題点」と題して明らかにしたのが『東国文献備考』の改竄説である。この改竄説は、外務省の小冊子『竹島問題を理解する10のポイント』でもとられているが、韓国側研究者からの反証はなされていない。なお金柄烈氏は私との論争を無断で『独島なのか竹島なのか』(1997年)と『独島論戦』(2001年)に転載した。従って韓国側の研究者にも拙稿に触れる機会もあっただろうが、寡聞にして、その拙稿が論文目録の中に記載されたものは見たことがない。
注2.朴炳渉・内藤正中著『竹島=独島論争』「歴史資料から考える」(2007年)、「『世宗実録地理志』と于山島」(115頁~117頁)や池内敏著『竹島‐もう一つの日韓関係史』(中公新書、2016年・10~15頁)では、あえて草稿段階の『世宗実録地理志』を論拠として、『世宗実録地理志』(「蔚珍縣条」)の于山島は独島としたのである。
それにこの『世宗実録地理志』(「蔚珍県条」)の本文に記された于山島は、その分註に引用された『太宗実録』の「条」に由来し、欝陵島のことであった。それが『新増東国輿地勝覧』の「蔚珍県条」では、本文に于山島と表記しながら、分註でも「一説于山欝陵本一島」として、その所在を明確にしていないのである。それが後世の『輿地図書』や『大東地志』のように、『新増東国輿地勝覧』に依拠しながら、その本文からは于山島を削除しているのは、于山島が実在しない島嶼だったからである。
注3.朝鮮総督府中枢院編『校訂慶尚道地理志慶尚道続撰地理誌』(昭和13年刊)、その『慶尚道地理志』の序に、「規式に略して曰く」として「海中諸島。水陸之遠近」とあり、同書の巻首には、規式が「一、諸島陸地相去水路息数、及島中在前人民接居、農作無▲写事」と記されている。(▲はもんがまえに弁)
注4.慎■廈著『独島領有権に対する日本主張批判』(224~225頁)、李漢基著『韓国の領土』(235頁)、宋炳基著『欝陵島と独島』(52頁)等(■はかねへんに庸)。『実事求是』第73回では「戦後、申奭鎬氏が1948年に『史海』の創刊号で「独島所属に対して」」としていましたが、「1960年に申奭鎬氏が『思想界』で「独島の来歴」」と訂正して転載しました。
注5.韓百謙『東国地理誌』三十六丁、新羅の「封疆」、于山島のみを表記して、その後に『東国輿地勝覧』の「蔚珍県条」を引用。李孟休『春官志』等
注6.『訥斎集』巻六「附録」、徐居正「南原君家乗記」十八丁、徐居正は梁誠之が関与した書籍編纂について、次のように伝えている。「治平要覧、高麗史全文、全史節要、世宗文宗実録を撰し、又申叔舟と、世祖睿宗実録、魯山日記を修め。又教を奉じて、列聖御製詩、皇極治平図、龍飛御天歌、海東姓氏録、東国図経、五倫録、三綱史略、農蚕書、牧畜書、諭善書、時政記、八道地図、八道地理志、沿邊防戍図、東文選、東国輿地勝覧等の書を集(あつ)む」
注7.拙稿「竹島論争の問題点」(『現代コリア』第383号所収、1998年7・8月号)、拙稿『韓国の竹島教育の現状とその問題点』(「知っておくべき竹島の真実2」(29頁~44頁)、第4期島根県竹島問題研究会編、2018年)
注8.竹島問題研究会編『竹島紀事』42頁
注9.『韓日古地図の中の朝鮮半島、東海そして独島』(309頁)でも『欝陵島図形』の「所謂于山島」に関して、「やはり竹島を描いたものと判断される」としている。ただしこの「所謂于山島」の于山島は、金鍾根氏もその竹島をチクトウと表記しているので、竹嶼のことである。
注10.「刻石立標」は1711年(辛卯五月九日)、欝陵島の倭船倉に到泊した捜討使の朴錫昌が五月十四日、同所より船を待風所に移動させる際に、「以為日後憑考」(以て日後の憑考と為す)として、その証として欝陵島(道洞)に設置したもので、現存する。『欝陵島図形』ではその「刻石立標」を東側に表記し、西側には「刻板立標」と表記している。この「刻石立標」と「刻板立標」は、朴錫昌の『鬱陵島図形』から始まったのである。従って「欝陵島図」で「刻石立標」と「刻板立標」が表記されていれば、それは朴錫昌の『欝陵島図形』系統の地図ということの証左である。
(島根県Web竹島問題研究所「実事求是」第73回より転載)