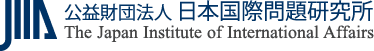第2次トランプ政権は、アメリカの歴代政権とは異なる前提に立った安全保障政策を追求するとみられる。2025年3月現在、個別具体的な政策として打ち出されている取り組みは限られており、今後それらは変化していくであろうが、その影響は諸外国に多大な影響をもたらすと思われる。本シリーズでは、政権の安全保障政策に関する主な要素を整理して、そのインプリケーションについて予備的に考察してみたい。第1回目は、第2次トランプ政権にとっての脅威認識および死活的利益、ならびに日本へのインプリケーションについて検討する。
ポスト冷戦期のアメリカの歴代政権は、民主主義、法の支配、人権といった価値や規範の共有度に応じて敵・味方を識別してきた。「ならず者国家」ないし「悪の枢軸」と呼ばれたイラン、北朝鮮、サッダーム体制下のイラク、アサド体制下のシリア、カダフィ体制下のリビアなど、アメリカの経済制裁ないし武力行使の対象とされてきた国々は、国内統治では重大な人権侵害に及び、対外行動では国際的なルールに対する重大な違反を重ねていた。近年、「現状変革国家」ないし「戦略的競争相手」と性格づけられるようになった中国やロシアは、様々な形で力を増勢させるのみならず、アメリカの重視する価値や規範に反する形で力を行使した結果、アメリカの反発を買うようになった。他方、民主主義、法の支配、人権といった価値や規範を共有する国々を同志国として優遇してきた。
これに対してトランプ大統領は、民主主義、法の支配、人権といった価値や規範の共有度というレンズを通して他国を測るわけではなさそうである。価値を共有する同盟国・同志国を優遇するわけではないし、権威主義体制の指導者との取引も厭わない。こうした姿勢の根底には、二つの意識があると思われる。
第一に、アメリカの平和と繁栄が、他の国・地域の平和と繁栄から切り離されて存立しうるという意識があるとみられる。それ故にアメリカが武力を行使してでも守るべき死活的利益の概念が歴代政権よりも縮小し、アメリカの政治的独立と領土的一体性に限定されている可能性がある。死活的利益の範囲が縮小すれば、自ずと何が脅威で何が脅威ではないかという理解も変化する。これまでアメリカにとって死活的利益とされてきたものがそうではなくなるヨーロッパのような地域では、安全保障のコスト・リスクの分担をめぐって、当該地域の同盟国はアメリカに依存できないという不安と焦燥感に駆られ、同盟関係は緊張含みとなる。中東では、イスラエルを軍事的・地政学的な優位に立たせ、イラン弱体化を実現した上で関与を後退させようと企図している可能性がある。トランプ大統領にとって、アメリカが戦争を覚悟して他の国・地域を守るということは自明の前提ではないので、地域紛争は第一義的には直接の当事国や紛争の帰趨に大きな利害を有する地域諸国がそのコスト・リスクを負って解決すべきということになろう。
第二に、安全保障問題なるものは、全て諸国家の利害の衝突から生じているので、様々な圧力を背景に、利害の調整を図る交渉を行い、互いに合意できる均衡を取引(ディール)としてまとめれば、安全保障問題は解決可能という意識があるとみられる。トランプ大統領の中では、武力を行使して全面戦争のリスクを冒すべき利害は、アメリカの本土と国民に直接関わるものだけであろう。他の大国の利害が関わる西半球外の地域紛争については、アメリカが全面戦争のリスクを冒すべきではなく、交渉を通じた取引で決着すべきものだと考えている可能性がある。一方、アメリカよりも力が劣る格下の相手に対しては、アメリカに有利な決着が図られるべきという考え方の下、経済制裁はもちろん、必要に応じて武力による威嚇も行いながら、相手にアメリカの要求を受け入れさせる強制外交を行うことを厭わない。
こうした意識に根差した安全保障観に立てば、トランプ大統領としては、ロシアと中国それぞれを相手に取引を通じて新たな均衡を実現し、安全保障問題のリスクを低下させたいということになろう。事実、トランプ大統領は2025年2月13日に、ウクライナと中東での問題を決着させた後に、中国およびロシアと核兵器に関する対話を進め、両国とともに国防予算を半減させたいと述べており、いわゆる脅威削減のアプローチをとる意向を示唆している。米中露三国間の核合意を実現できるかどうかはともかく、トランプ大統領が、西半球以外の地域安全保障への軍事的関与を後退させるとともに、中露などの大国と新たな均衡を形成するという思惑を持っているとすれば、トランプ大統領は、アメリカ社会を直接侵食しているとみなす不法移民やフェンタニル、組織犯罪、テロリズム、北朝鮮・イランの大陸間弾道ミサイル(ICBM)、そして中国によるアメリカの経済的・技術的利益の収奪といったものを脅威として認識しているとみられる。このことはすなわち、北米・西半球地域の防衛を最優先化することを示唆しており、それ以外の地域に地政学的な脅威があるとしても、それは関税もしくは武力による威嚇を背景にしたディール外交で「非脅威化」できると考えている可能性がある。
第1次政権では、トランプ氏が国際主義的な共和党穏健派の人脈を頼ったがために、理念本位の脅威認識に基づいて中国とロシアを「現状変革国家」とみなす戦略文書を発出したが、第2次政権はそれとは異なる一国主義的な安全保障観に立った脅威認識が戦略文書で打ち出されていくことも想定しておくべきであろう。外交・安保閣僚らは、インド太平洋地域における中国の地域覇権確立を阻止すべきとの考えを持っているようであり、それ故に対中タカ派だともいわれている(ヨーロッパと中東への軍事的関与を後退させ、中国への対抗にリソースを集中させるべきと主張する優先主義者)。そうした政権内プレイヤーらは、アメリカの二国間同盟や、豪州、韓国、フィリピンなどとの三国間協力、日米豪印のクアッドなどを対中バランシングに有用だとみている。ただし、そうした優先主義者の対中タカ派が、政権内で一国主義勢力を相手に、どこまで影響力を行使できるかは不透明であることも注意する必要があろう。
日本にとって決定的に重要なのは、やはりトランプ大統領と外交・安保閣僚が、日本および西太平洋地域にアメリカの死活的利益があるとみているかどうかということであろう。両者が一致した見方を持っているとは限らないが、大統領の意向は絶大な意味を持つ。特に台湾が、アメリカが中国との戦争を覚悟してまで守るべき死活的な利益であるという認識を大統領が持っているかどうかは極めて重大な問題となる。もしトランプ大統領にとって、台湾はアメリカの死活的な利益ではないということになれば、この地域におけるアメリカの対中抑止力の信頼性は大きく低下することになる。この点についてトランプ大統領は、中国とのディールに支障が出るので、中国が台湾に侵攻した場合の対応を明らかにしたくないとして、意図的に曖昧にしてきた。
これまで日本の安全保障政策の根幹は、インド太平洋地域の平和と安定のためにアメリカをこの地域に関与させるということにあったが、その大前提として、アメリカが西太平洋地域ないし第一列島線を死活的利益として定義するということがあった。だからこそ地域諸国はアメリカと利害を共有し、西太平洋地域の現状を一方的に変更して諸外国の利害を侵食しようとする中国や北朝鮮を安全保障上の挑戦ないし脅威として認識してきた。換言すれば、アメリカが西太平洋地域を死活的利益と定義するという中核的な要素の上に、あらゆるアメリカとの防衛協力や安全保障協力が構築されてきたといえよう。日本は、アメリカの死活的利益が縮小的に再定義され、脅威認識が変容する兆しを見逃さないように細心の注意を払って観察するのは当然として、それが現実化した場合に、日本の国家安全保障戦略の何をどのように変え、何を変わらず続行すべきなのかを冷静に検討する必要があろう。そのような検討の結果を実行するかどうかの判断は深慮を重ねた上で下されるべきであろうが、少なくともそのような検討を行うべき局面に入ったといえよう。
(つづく)