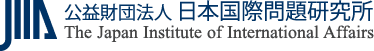「国問研戦略コメント」は、日本国際問題研究所の研究員等が執筆し、国際情勢上重要な案件について、コメントや政策と関連付けた分析をわかりやすくタイムリーに発信することを目的としています。
米欧関係の亀裂
2025年2月は米欧関係にとって一つのターニングポイントとなった。2月10日からアメリカのヘグセス国防長官が訪欧し、ドイツ、ベルギー、ポーランドを訪問した。国防長官は訪問先での記者会見で「米軍の欧州駐留は永遠ではない」と表明し、欧州は防衛予算を増額すべきだと進言した。さらに、ウクライナへの米軍派兵を改めて否定し、ウクライナのNATO加盟についても否定的な見解を示した1。
米国の国務長官のこうした発言について欧州各国が動揺する中で、続いて2月14日から16日にかけて欧州最大規模の国際会議であるミュンヘン安全保障会議が開催された。欧州中の政策決定者や有識者の注目が集まる中で、米国のJ. D. バンス副大統領が演説し、欧州にとっての最大の脅威はロシアでも中国でもなく、欧州域内にあるとの認識を示すとともに、欧州各国の言論の自由の統制と移民問題について苦言を呈した2。
こうした発言は、とりわけ連邦議会選挙を1週間後に控えたドイツに強く向けられたと考えられた。すでにイーロン・マスクは2024年12月時点で極右政党のドイツのための選択肢(AfD)を応援していることを公言しており、そして彼らを取り巻くドイツの政治環境について苦言を呈していた。バンス副大統領の語った「言論の自由の統制」に対する批判が、AfDに対する応援であり、極右政党を「弾圧」するドイツの政治状況への批判であることは明らかであった。更に、ミュンヘン市内ではこの前日にも労働組合のデモに車が突っ込む事件が発生しており、移民問題との関連が捜査される中での発言であった3。
欧州は一致団結
ミュンヘンでのバンスの演説は欧州内に大きな動揺をもたらした。ショルツ首相やカッラス欧州連合外務・安全保障政策上級代表などは不快感をあらわにし、多くの欧州リーダーも同様の反応を見せた4。この点において、欧州の政治家は不本意ながらもアメリカに対する警戒感で一致団結し、欧州の防衛を自分たちだけで考える時が来たのだという論調も生まれた。また、バルト三国のようにロシアへの警戒心が強く、すでに防衛費も対GDP比でゆうに3%を超えていた国々は、ようやく他の欧州諸国が防衛費の拡充に前向きになったことを前向きに捉える雰囲気も見られた5。
連邦議会選挙を1週間後に控えたドイツにおいても、バンスの演説は政策論議に大きな変化をもたらした。ミュンヘン安全保障会議から遡ること約2週間前に、ドイツ国内は大きく揺れていた。最大野党であり、連邦議会選挙で第一党になることを予測されていたキリスト教民主同盟(CDU)が不法移民を国境で送還することを視野に入れた決議を議会に提出し、これに極右政党のAfDが賛同して可決されたことが国内で大きな批判を浴びていた。
CDUは昨年の党大会でAfDとの連立交渉を完全に否定し、また、その前からすでに緑の党やSPDもAfDとの連立を否定しており、ドイツ国内の政治状況においてAfDは未だ「極右」の扱いを受けている。決議に法的拘束力はないものの、こうした政党と協力をしたことは、国内では大きな衝撃を持って受け止められた。主要都市では同法案を批判するデモが次々に実施され、また、緑の党や左翼党といった左派政党の入党希望者はこれまでにない規模で増加した67。一方で、こうした批判に対してメルツは「間違った勢力に応援されたからといって政策が間違っているとは限らない」と反論した8。最終的にこの決議の法案化は否決されたが、その原因がCDU党内の造反であったことに鑑みても、いかにAfDとの協力が現在のドイツ内でタブーであるかが窺われる。
こうした直前の状況から考えると、メルツがバンスの演説に対してどう反応するかは推し量りづらいところがあった9。司会者にバンスの演説についての感想を聞かれたメルツの答えは「自分たちもアメリカの選挙を尊重する。同じようにアメリカも我々の選挙を尊重してほしい。」というものであった。この意見表明は拍手を持って迎えられ、右派左派問わず、バンスの演説がドイツ国内で反発をもって受け止められたことを示した。こうして、選挙ひと月前に国内の世論を二分した論争は徐々に収束し、いわゆる中道政党の間で一種のコンセンサスが形成された。結果としてバンスは欧州を、そして選挙を控えたドイツを団結させたと見ることもできるだろう。
2月末にはホワイトハウスでゼレンスキー大統領とトランプ大統領が会談をするも、両者は物別れに終わった。会談の様子は全世界に中継され、トランプ大統領とバンス副大統領がゼレンスキー大統領を叱責するそのさまは全世界に衝撃を与えた10。欧州諸国も直ちに反応し、多くの国がウクライナとの連帯を表明した11。米欧関係はますます悪化の一途を辿り、一方で、欧州はますます連帯を強めているように見える。メルツは連邦議会選挙が終わるとすぐに「安全保障面でのアメリカからの自立」を目指すと主張し、また、フランスのマクロン大統領に核の傘の拡大を持ちかけたことが明かされた12。ウクライナ戦争開戦から3年が経過し、ついに欧州は団結して「戦略的自律」の道を歩み始めたのである。
足元で残る課題
一方で、これで全ての課題が解決されるわけではない。まず、欧州の「戦略的自律」のために必要とされる道のりの長さについては、すでに様々な角度から議論が始まっている。例えば、The Sunday Timesでは、英国軍隊がいかに作戦の計画、管理、実行についてアメリカ軍に頼っているかについて、定量的な観点から詳しく特集された13。これによると、英国陸軍の兵力はナポレオン時代以降最小規模であり、海軍はアメリカ軍の補給艦抜きには作戦実行能力を持たず、F35を74機購入するという同盟国との約束は全く果たされていない。また、インテリジェンスについてもアメリカの衛星から収集された情報に頼っており、いかに英国の作戦そのものがアメリカの政策の中に埋め込まれてきたかを物語っている。
同様のことは、フランスにも当てはまる。そもそも伝統的に「戦略的自律」を掲げてきたのはフランスであり、とりわけマクロン大統領はこの考え方を推進してきた人物である14。この意味で、同大統領が核の傘の拡大に言及するのは、フランスが核保有に進んだ歴史とも合致する流れであり、また、それが独仏協力の中で考えられていることも、欧州にとって望ましい流れであると言える。一方で、現在フランスが保有している核兵器は約300発程度で、これはロシアおよびアメリカの核保有数には到底及ばない。更に、フランスが有する核兵力は潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)に集中しており、これだけでは効果的に段階的なエスカレーションを形成することができない。フランスは核の傘拡大のためには、改めてその核戦略を見直す必要がある。そしてそれは一朝一夕に解決される課題ではない。
また、核の傘拡大のアイディアそのものにも疑問は残る。結局のところこれが何を意味するのかは、まだそれほど明確になっていない。伝統的な核共有のことを指すのであれば、それがいかに難しい課題であるかはすでに多くの研究が指摘してきたところである15。安全保障政策が分かち難く主権と結びつく以上、いかに核の傘が共有されようとも、最終的な核のボタンは核保有国が握り続ける。こうした問題についても、まずは同盟国間での政治レベルでの調整が必要となり、時間を必要とするだろう。
米欧関係の悪化に伴い、欧州はますます防衛支出を増加させると考えられる。SIPRIの発表によると、すでに、欧州の防衛支出は2019年と比較して倍増している。一方で、こうして増額された支出が結局のところ何に向けられてきたかというと、それはF35などを中心とした、米国製の最新式兵器の購入である16。欧州が戦略的自律を目指すのであれば、その戦力拡大はやはり欧州地域で調達されることが本来望ましい。こうした議論は欧州域内でも活発になっており、欧州内の防衛産業は一種のブームとなっている17。それでも、世界全体のシェアで考えると欧州域内の産業規模はアメリカには遠く及ばない。産業全体の「底上げ」にもまた、かなりの時間を要するだろう。ウクライナ戦争開始から3年が経過し、欧州の頭越しに停戦交渉も行われている中で、欧州の戦略的自律は時間との戦いでもある。