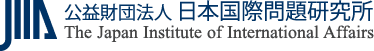「国問研戦略コメント」は、日本国際問題研究所の研究員等が執筆し、国際情勢上重要な案件について、コメントや政策と関連付けた分析をわかりやすくタイムリーに発信することを目的としています。
2024年4月に岸田総理とバイデン大統領は、自衛隊と米軍の指揮統制の近代化と連携の強化で合意した。この合意をうけて、2025年3月24日に発足した自衛隊の統合作戦司令部と、今後在日米軍におかれる予定の統合軍司令部の連携を目指すことになっている。これは、日米の作戦および能力のシームレスな統合を可能にし、平時および有事における自衛隊と米軍との間の相互運用性・計画策定の強化を可能にするため、70年以上におよぶ日米同盟の枠組みを大きく向上させる取り組みになることが期待されている。
この方針は、2025年2月の首脳会談で石破総理とトランプ大統領によっても確認された。しかし、米国内の報道では、連邦政府の効率化を目指す観点から在日米軍の強化を見直す動きがあるという。計画を取りやめれば、およそ12億ドルの経費が節約できると試算されているが、一方で太平洋での米軍の能力低下や、日本との「政治的リスク」を招く可能性があるとも指摘されている。以下では、在日米軍の強化がなぜ重要なのか考えてみたい。
日米同盟は朝鮮戦争という地域紛争を戦うために生まれた。日米が今指揮統制面での連携強化を行うのは、パワーバランスの変化によって再び地域で紛争が起こる可能性が高まっているためである。抑止の強化が必要なのはもちろんだが、抑止が破断した場合の対処をより有効に行うことが求められているのである。ただ、それは単に地域紛争を戦うという"原点への回帰"ではない。同盟を近代化させた上で、領域横断作戦とハイブリッド戦に特徴づけられる現代戦を共に戦うための"未来への回帰"である。
元々、日米安全保障条約は「モノとヒトの交換」だといわれ、米国が兵力を提供し、日本が基地を提供するというのが始まりであった。これは朝鮮戦争勃発時、米国が日本に期待したのが施設の提供と後方支援だったからである。しかし、その非対称性は長年の両国の努力によって相当程度解消された。自衛隊が役割を増大させ、日本有事はもちろん、日本が直接攻撃を受けていない場合でも、米軍に対する支援ができるようになったからである。日本が限定的ながら集団的自衛権を行使できることを前提とした2015年の平和安全法制は、その1つの帰結であった。
日米が共に戦う関係になる上で課題となってきたのが、指揮統制面での調整であった。米軍では1980年代以降統合運用が進み、自衛隊も2006年から統合運用を本格化させてきた。しかし、2011年の東日本大震災への対応時に、防衛大臣の補佐と部隊の指揮の両方を行う統合幕僚長の負担が大きく、統合運用体制の見直しが議論されるようになった。また、統幕長と米側の調整窓口も複数にまたがることから、日米の指揮統制面での調整面での課題も指摘されるようになった。このため、2022年の国家安全保障戦略で3自衛隊の運用を一元的に行う統合司令部組織の創設が決められ、統合幕僚長は防衛大臣の補佐を主に行うこととなった。
指揮統制の変更は容易なことではない。統合幕僚監部および各幕との関係、防衛省内局とのバランスなど、政治的に難しい問題である。しかし、それらを克服して日本側が統合作戦司令部の創設を決めたことが、米軍の指揮統制の見直しにつながった。在日米軍司令官は作戦指揮権を持たず、在日米軍の運用はインド太平洋軍司令官が行う。しかし、効果的な指揮統制の調整を考えれば、日米の統合運用司令官が東京にいることが望ましい。朝鮮戦争時、マッカーサー極東軍司令官は東京から米軍の指揮を取ったが、3・11のトモダチ作戦でも太平洋艦隊司令官がハワイから東京に来て米軍の指揮を取った。米軍内には指揮統制の見直しには慎重な声もあったが、日本側が統合体制を整えたことが米側を刺激し、在日米軍の運用のため統合軍司令部を東京に置くことが決まったのである。
日米の指揮統制面での連携強化は、両国が現代戦を共に戦う態勢を整え、対処力を向上させる上で極めて重要である。それが抑止力の強化につながるのである。指揮統制の調整を通じた運用面での連携強化だけではなく、負担が軽減された統幕長と米戦略軍司令官のコミュニケーションの確立により、拡大抑止の信頼性を向上させることも可能となるであろう。米軍の自衛隊や民間施設へのアクセスの強化、極超音速技術の共同研究、日本国内での米軍の整備・補修など、両国の協力関係はますます深まっている。2025年3月30日に開かれた日米防衛相会談では、指揮統制の連携強化について確認され、統合軍司令部創設に向けた在日米軍改編の第一段が始まったことが表明された。今夏にも日米2プラス2が予定されているが、この"未来への回帰"の重要性について、引き続き閣僚レベルで再確認する必要がある。