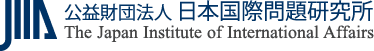信号連立政権崩壊と解散総選挙
ドイツ連邦政府では2024年11月6日にショルツ政権の一翼を担っていた自由民主党(FDP)党首のリントナーが財務大臣職を辞したことを機にFDPが信号連立を離脱し、少数与党となった。連立政権は長らく予算について議論が続いており、議論に折り合いがつかなかったことが直接の原因となって連立政権は崩壊した1。予算をめぐる論争の始まりは、信号連立政権がコロナのための予算を他の目的に利用しようとしたことに始まる。
ドイツではGDPに対して0.35%以上の国債を発行することが禁じられている(基本法第109条)2。債務ブレーキと呼ばれるこの規則は、ドイツの厳しい財政規律を象徴するものと捉えられてきた。債務ブレーキがドイツ基本法に組み込まれたのは、第二次世界大戦前のハイパーインフレが原因である。このインフレによって国民生活が疲弊したことがナチ党台頭に繋がった一つの要因である以上、戦後ドイツは二度とこうした事態に陥らないための規則を必要とした。一方で、基本法115条において、自然災害や非常事態においては限定的に借入限度額を超過することができると規定されている3。
2020年から数年にわたって世界を悩ませたコロナウイルスとそれによって引き起こされた事態は、115条に規定されている「非常事態」と判断され、当時のメルケル政権は特別に0.35%を超えて国債を発行することができた。しかし2021年年末にもなるとコロナは一応の収束を見せ、コロナ基金は予想以上に使われないことが明らかになった。このため、2021年11月に発足した信号連立政権はこの基金を主にグリーンとエネルギートランジションに利用することを前提とした連立交渉を展開し、連邦レベルでは史上初の三党連立政権として誕生した4。しかし、2023年11月に連邦憲法裁判所によってこの「流用」が違憲であると判決が下され、以降、連立政権は減少した予算と公約の折り合いをつけるべく議論を続けていたが、ついにこれが1年越しに崩壊した形となる5。
選挙結果
少数与党となったショルツ政権は12月に連邦議会で信任決議を提出し、これが否決される形で2月23日に前倒しで連邦議会選挙が行われることとなった6。史上4度目となった前倒し選挙は国内の強い関心を集め、投票率は東西ドイツ後最高の82.5%を記録した。主要政党の得票結果は以下の通りである7。
| 2025年ドイツ連邦議会選挙 | 得票率 | 前回比 | 議席数 | 前回比 |
| キリスト教民主同盟(CDU) | 22.6% | +3.6% | 164 | +12 |
| キリスト教社会同盟(CSU) | 6.0% | +0.8% | 44 | -1 |
| ドイツ社会民主党(SPD) | 16.4% | -9.3% | 120 | -86 |
| 自由民主党(FDP) | 4.3% | -7.1% | 0 | -91 |
| 緑の党(Bündnis 90/Die Grünen) | 11.6% | -3.1% | 85 | -33 |
| 左翼党(Die Linke) | 15.9% | +4.9% | 64 | +25 |
| ドイツのための選択肢(AfD) | 20.8% | +10.4% | 152 | +69 |
| ザーラ・ヴァーゲンクネヒト同盟(BSW) | 4.98% | 0 | -10 | |
| 南シュレスヴィヒ選挙人同盟(SSW) | 0.2% | ±0% | 1 | ±0 |
一見してわかる通り、信号連立を構成した3党は軒並み得票率を落とした。特に、信号連立を崩壊に追いやったと目されたFDPは得票率が5%を超えず、議席を失うこととなった8。社会民主党(SPD)、そして前回最大の躍進を遂げた緑の党も大きく議席を減らし、SPDは史上最低の投票率となった。これに対して、第1党となったのはキリスト教民主・社会同盟(CDU/CSU)である。一つの会派を形成する両党合わせて28.6%を得票した。また、前回2021年選挙に比べて最も得票を伸ばしたのがドイツのための選択肢(AfD)である。得票率は倍増し、第2党の座を獲得した。
「極右の躍進」?
上記の結果を以て、今回の連邦議会選挙で極右政党が躍進したと見る向きもあるが、これは二つのポイントから正しくない。第一に、2024年6月に行われた欧州議会選挙の結果と見比べるとわかるように、すでに2024年の時点でAfDは16%近くを得票しており、この時と比べてそれほど大きく得票率を増やしたわけではない9。
| 2024年欧州議会選挙 | 得票率 |
| キリスト教民主同盟(CDU) | 23.7% |
| キリスト教社会同盟(CSU) | 6.3% |
| ドイツ社会民主党(SPD) | 13.9% |
| 自由民主党(FDP) | 5.2% |
| 緑の党(Bündnis 90/Die Grünen) | 11.9% |
| 左翼党(Die Linke) | 2.7% |
| ドイツのための選択肢(AfD) | 15.9% |
| ザーラ・ヴァーゲンクネヒト同盟(BSW) | 6.2% |
| 諸派合計 | 14.2% |
第二に、この数年でAfDが得票を増やしていることは確かであるが、それでも得票率が20%に過ぎないという事実である。この点で注目すべきは、彼らの支持者の属性にある。まず、AfDの支持者は男性が多く、女性支持が少ない10。また、労働者(いわゆるブルーカラー)と無職の支持率が特に高いことも注目に値する。ドイツ全体における労働者人口は減り続けており、2023年時点では全人口の10%程度であることを考えると、今後AfD支持者が更に飛躍的に上昇することも考え難い11。
一方、今回の選挙で台風の目となったのは左翼党である。2023年には政党内から一部党員が離脱する形でザーラ・ヴァーゲンクネヒト同盟(BSW)が誕生し、党勢を落としていたことを考えると、今回の16%近い得票率は驚きに値する。2021年選挙と比較しても5ポイントほどの増加であり、左翼党の「復活」は印象深い。左翼党支持者の属性で興味深いのは、まず女性票の高さである。また、若年層にも人気が高く、特に18-24歳の層での得票(25%程度)は全体の平均をはるかに上回る12。この層は2021年連邦議会選挙の際に緑の党を支持した層と重なっており、2021年に緑の党の躍進を助けた支持層が、今回は左翼党の躍進を助けたと考えることができるだろう。
「安定した政権運営」になるのか?
AfDと左翼党が得票を伸ばしたのは確かであるが、それでも全体の60%近い投票者がいわゆる「中道政党」を選んだことに注目する評者も存在する13。結果として、CDU/CSUとSPDによるいわゆる大連立で議席の過半数を超えることも決定し、両党は4月9日に連立協定を成立させた14。これによって、約4年ぶりの大連立が復活することとなった。16年続いたメルケル政権もその大半を大連立で運営しており、再び安定した政権運営が行われると見る向きもある。
一方で、こうした見方はあまりに楽観的に過ぎるように思える。以下、3つの観点から今後のドイツ連邦共和国の政治について考察を加える。第一に、今後の大連立が「安定した」政権であるかは疑問の余地がある。大連立政権が初めて生まれたのは1966年のことであり、この時の与党の議席占有率は実に90%を超えた。まさしく「大」連立であり、むしろ議会内の議論に意味がなくなったとさえ見ることもできた15。一方で、今回の大連立は得票率では50%に及ばず、議席占有率も52%に過ぎない。議会では過半数を辛くも超えたに過ぎず、このため、法案制定には党内からの造反に常に気を配る必要がある。中道政党の得票率の低下は数十年続く長期トレンドであり、短期的にこの傾向が変わることはないだろう。
第二に、中道政党内の「不和」にも目を向ける必要がある。上記のように大連立は辛くも議席の過半数を獲得したに過ぎず、より安定した政権運営のためにはもう一つの中道政党である緑の党を政権運営に加えることも考えられた。しかしこの提案についてはCSUが反対し、連立交渉は行われなかった。CSUは選挙戦の最中から緑の党との連立については否定的な立場を取り、同党に対する批判を隠そうとしなかった16。また、選挙戦の最中にはメルツ党首がFDPへの投票は「無駄になるので」CDUに投票するよう呼びかけるなど、中道政党といえども政党間での調整はもはや簡単ではない17。CDU/CSUとSPDの間にも注意は必要であり、CDUが提出した不法移民に関する決議をめぐっては両党の構成員は強く反発している。税金や年金も両党の一致が難しいとされており、連立交渉が成立するまで実にひと月以上を要した18。
第三の観点として、今回の選挙の最大の特徴とも言える「不人気」について触れたい。メルツ党首率いるCDUは確かに第1党を獲得したが、その支持基盤は盤石には程遠い。メルツは選挙戦を通じて終始その支持率が低く、しかしながら信号連立をはじめとするその他の候補者がさらに低い支持率であったため、消極的に選ばれたに過ぎない。メルツの支持率の低さにはいくつかの要因があろうが、その一つが彼の度重なる不用意な発言にあることは否定できないだろう。過去には移民をめぐって事実と異なる発言をしたこともあり、その度に他党からの批判、そして支持率の低下を招いてきた19。中道政党間の調整が難しくなっている中で、首相による問題発言によって政権与党内部から離反者が出ないように改めて気を付ける必要がある。
このように、今後のドイツの政権運営はそれほど楽観的になれるものではない。安定した政権運営のためには、何より、中道政党の党勢復活が必要不可欠である。そのためには国民が重視している問題―治安問題と社会保障―に重点的に取り組む必要があるだろう。それはまさにAfDや左翼党が党勢を獲得している理由であり、結局のところ、これらの問題を解決することでしか中道政党の復活はない。こうして引き続き、次期政権の目は主に内政に向かうことになるだろう。
これらの問題を解決する一つの希望としてにわかに注目が集まっているのが防衛産業である。信号連立が環境問題やエネルギー・トランジションに重点的に力を入れていたことは既に述べた通りである。しかし、注力も虚しく予算に穴が空いたことで政権の思惑は失敗した。また、市場においても、中国産のEV車に押され続け、基幹産業である自動車産業の2024年の業績はかなり悪化した。そもそも政策志向の異なる信号連立を違った観点からまとめ上げたのが環境政策などであったように、次なる同床異夢の政策が防衛産業であるようにも見受けられる20。SPDにとっては何より雇用を守ることが重要であり、CDUにとっては2期連続のマイナス成長から脱却することが必要である。アメリカが欧州防衛から遠ざかろうとしていることがある種の追い風となって、3月には防衛政策に関しては債務ブレーキの対象外とすることも決定された。ドイツの積極的な姿勢は他の欧州諸国からは基本的に歓迎されている21。
一方で、本政策が次なる「環境政策」にならないとも限らない。防衛産業も当然ながら一つの産業であり、そこには市場原理が働く。政権が後押ししたからといって市場で勝てるとは限らないのは既にEV車の例で散々見たところである。また、新しい連邦議会で35%を占めるのはウクライナに対する武器支援を否定し、ウクライナ戦争の即時停戦を唱えているAfDと左翼党である。両党はNATOについても従来から批判的な立場を崩しておらず、脱退すら支持する立場である。今回両党が支持を拡大したのは両党の外交政策とはあまり関わりがないとは捉えられているが、それでもこうした勢力が議会内において議席を増やしたことは注意しなくてはならない。だからこそ、政権誕生前、さらには議会招集前に積極的に政策転換を目指していたと考えられるが、こうしたやり方を非民主主義的だと批判されたら反論は難しいのではないか。新政権が遂に誕生した今、今後の議論に注目が集まる。
(2025年4月11日脱稿)